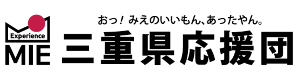《三重の魅力ピックアップ》
海の青を湛えた、美しくも優しい器の数々
天水窯の代名詞といえる印象的なブルー
学生の頃、いろんな海でサーフィンをしていた稲垣竜一氏。海にもいろんな表情があり、これを萬古で表現したと学生の頃より考えていました。
波のように揺らぐ「うみのいろ」。炎にも夕日にも似た「蘇芳香(すおうこう)」など、無限に編み出される美しい色彩は、唯一無二、天水窯の真骨頂です。ただ一色のブルーではなく、1つの作品でいろんな色のブルーの表情を楽しめるのが特徴的です。
2016年5月に行われた伊勢志摩サミットでは各国首相夫人が出席した「配偶者プログラム昼食会」にて、稲垣竜一氏が作陶したワインカップが採用されました。
ワインカップはブルーで、三重の賢島・伊勢志摩の美しい海を表現。ひとつひとつ色合いの変化を微妙に持たせ、ゆらぎや深さを想像させます。
先代の系譜を受け継ぎながら、新たな創意を重ね、進化を続ける天水窯。土や釉薬の調合を始めとする作業工程ひとつひとつ“すべて手作り”にこだわっています。とてもアナログだけどAIにはない感性や個性、そして何よりも作り上げるための時間や作り手の想いが吹き込まれる瞬間。
伝統を受け継ぎながらも土・釉薬・作陶家の個性を大切にし、試行錯誤を重ねながら理想のかたちを創り上げているからこそ、他にはない一点ものが創られていくのです。

料理などの彩りを際立たせる、優しいブルー
ブルーの器だとお料理を盛るのに使いにくいのではないかと思われるかもしれませんが、実際はとても使いやすいカラーで、あらゆるお料理を際立たせてくれます。
天水窯のインスタグラム(@tenzumama)では、稲垣竜一氏の奥様が実際に器を使われている様子を紹介しており、お洒落で上品ながらも温かい彩りに包まれる食事の数々をご覧いただけます。

全く同じものができないからこその面白さが、そこにある。
「長年親しんできたサーフィンも作陶も自然が相手。だから全く同じようにいかないからこそ面白い。」
そう語る作陶家の稲垣竜一さん。
同じ成形を施したり、同じ釉薬を使っても、ひとつひとつの器に色合いや佇まいの違いが出て、同じ作品ができることはありません。そこが四日市萬古焼の器の楽しみであり、多くの人が稲垣さんの作品に魅了される理由なのでしょう。
海の青を基調とする萬古焼を作陶する天水窯です。
その青は、釉薬(ゆうやく)の案配、窯の温度、タイミングなど、様々な要素が合わさって、窯の中で生まれる自然な色彩となります。窯から上げた作品は、予想しない彩りをみせる時があるといい、作家自身も完成は楽しみだといいます。
2代目の竜一さんは、父 太津男さんの背中を追い研究を続けていました。良質な作品を真似することで、技術が日々磨かれ、結果自分のオリジナルができたといいます。
現在は奥様とも協力し、家庭に馴染みやすい、食器として使いやすい作陶に挑戦しているようです。
伝統を継承し、次世代にあった器を、天水窯の研究はまだまだ続きます。
[企業名]三位陶苑
[出演]天水窯 二代目 稲垣竜一 他
| 基本情報 | |
|---|---|
| 住所 | 〒512-0902 三重県四日市市小杉町1875 |
| 電話番号 | 059-331-0504 |
| 公式サイト | http://www.tenzugama.com/ |
※情報は取材時のものであり、変更の場合があります。
| 動画リンク先 | |
|---|---|
| YouTube | https://youtu.be/YeJS_5t_Ww0 |